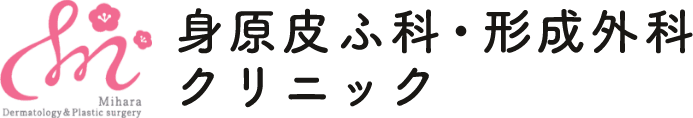ビタミン剤は安全?
当院では、ビタミン剤の内服については原則として処方しておりません。
この方針には、以下のような科学的な根拠と医療現場の現状に基づく理由があります。
保険適応に関する明確な基準
2012年に厚生労働省は、すべてのビタミン剤について以下のように定めました:
- 医師がその効果を有効と判断した場合。
- 疾患や症状の原因がビタミン欠乏または代謝異常であることが明らかである場合。
- 必要なビタミンを食事で摂取することが困難である場合や、それに準ずる状況。
これらに該当しない場合、ビタミン剤の処方は医療保険の対象外とされています。
エビデンスの不足と医療費の増加
ビタミン剤の多くは、科学的に効果が明確に証明されているとは言えません。「なんとなく良さそう」という慣習的な理由で処方されているケースも少なくありません。その一方で、2012年以降、ビタミン剤に年間約1000億円もの医療費が割かれており、この傾向は上昇しています。
過剰摂取によるリスク
ビタミン剤は適量であれば比較的安全とされていますが、過剰摂取や特定の状況下では副作用が発生する可能性があります。
脂溶性ビタミンのリスク
- ビタミンA: 頭痛、皮膚の落屑(らくせつ)、脱毛、筋肉痛、骨折リスクの上昇。
- ビタミンE: 出血傾向の増加、冠動脈疾患の死亡率増加(報告あり)。
- ビタミンD: 高カルシウム血症、腎障害、石灰化障害。
水溶性ビタミンのリスク
- ビタミンB1: 頭痛、不眠、いらだち、速脈、かゆみ。
- ビタミンC: 胃腸への影響(吐き気、下痢、腹痛)。
- 腎機能障害のある方が大量に摂取した場合、腎結石リスクが増加。
- 00_1_表紙_cs6_1220.indd「日本人の食事摂取基準(2020年版)」策定検討会報告書 厚生労働省 各論ビタミン
皮膚炎のリスクについての報告
最近では、ビタミンC誘導体を含む化粧品による接触皮膚炎(かぶれ)が複数報告されています。
(西日本皮膚科 2024年報告:田代ら 西日本皮膚科86(6)2024:564)
当院の方針
ビタミン剤は決して無害な万能薬ではありません。効果が明確でないにもかかわらず、副作用や医療費負担の増大が懸念されています。当院では以下の理由から、安易なビタミン剤処方を行っておりません。
- 科学的根拠に基づく医療の提供:ビタミン剤の使用には慎重であるべきです。
- 副作用リスクの回避:脂溶性・水溶性を問わず、過剰摂取などによる害が報告されています。
- 医療費の適正化:限られた医療資源を本当に必要な治療に活用する。
栄養バランスの良い食事を心がけましょう
ビタミンを効率よく摂取するためには、栄養バランスの整った食事が基本です。食品から得られるビタミンは、体内での吸収や利用効率が高く、副作用のリスクも低いです。
当院では、患者さんの健康を第一に考えた医療をご提供しています。


執筆者
身原 京美
院長 / 身原皮ふ科・形成外科クリニック
当院は広島で皮膚科専門医と形成外科専門医が診療を行う専門クリニックです。
皮膚科の新しい治療を積極的に取り入れる一方で、高齢者医療にも長年携わってまいりました。また、院長は2人の娘を持つ母として、赤ちゃんからお年寄りまで、幅広い年代の患者さんに対応しております。女性としての視点を活かし、シミやシワなど整容面のお悩みにも親身にお応えするクリニックを目指しています。
皮膚のお悩みは、お気軽にご相談ください。
取得資格
日本皮膚科学会認定専門医 抗加齢医学会認定専門医 日本褥瘡学会認定褥瘡医師 医学博士 日本熱傷学会学術奨励賞受賞 国際熱傷学会誌BURNS outstanding reviewer受賞