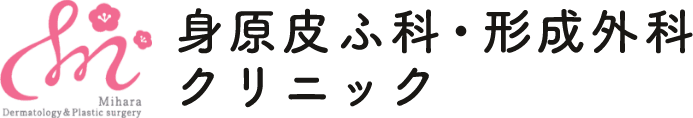足白癬・爪白癬(水虫)とは?
足白癬(あしはくせん)、爪白癬(つめはくせん)は、いわゆる「水虫」と呼ばれる白癬菌(はくせんきん)というカビの一種が皮膚や爪に感染することで起こる感染症です。
特に高温多湿の日本では発症率が高く、7人に1人が足白癬、13人に1人が爪白癬を有するというデータもあります(Foot Check 2023)。
放置すると治りにくく、周囲の人へ感染する恐れもあるため、早めの治療が重要です。
足白癬(足の水虫)の主な症状とタイプ
足白癬は主に以下の3タイプに分類されます。
1. 趾間型(しかんがた)
・足の指の間がジュクジュクして皮がむける
・強いかゆみを伴う
・特に小指と薬指の間に多く見られます
2. 小水疱型(しょうすいほうがた)
・土踏まずや足の縁に小さな水疱(みずぶくれ)ができる
・かゆみを伴うのが特徴
3. 角質増殖型(かくしつぞうしょくがた)
・かかとや足裏の皮膚が厚く硬くなり、ガサガサと乾燥した状態
・かゆみは少なく、乾燥やひび割れと間違えられやすい
爪白癬(爪の水虫)の症状
爪白癬は、主に以下のような変化が見られます。
- 光沢がなくなり変形する
- 爪が白く濁る、黄ばむ
- 厚くなり、ボロボロと崩れる


足白癬から爪白癬へと感染が広がることが多く、治療をしないと他の爪やご家族に感染する可能性があります。
当院での診断と治療
顕微鏡および抗原検査による確実な診断
当院では、足や爪の皮膚片を採取し、その場で顕微鏡検査を行って白癬菌の有無を確認します。
また、爪白癬で顕微鏡検査が陰性でも、抗原検査(保険適用)によって少量の菌でも検出可能です。
足白癬の治療法
- 外用薬(抗真菌薬)を1日1回、約2か月間塗布
- 症状のない部位にも広範囲に外用することが重要
- 角質増殖型の場合は、角質を柔らかくする薬剤も併用する
爪白癬の治療法
内服薬(飲み薬)
・ネドリール、イトラコナゾール、テルビナフィンなどを数か月〜半年服用
・肝機能が悪い方には不向きであり、服用中は定期的な血液検査が必要です
外用薬(爪専用)
・ルコナック、クレナフィンなどの爪白癬専用外用薬が保険適応
・毎日の塗布を1年以上継続する必要があります
再発予防・感染予防のためのポイント
白癬菌の再発や感染拡大を防ぐには、以下のような生活習慣の見直しが重要です。
- 毎日足を洗い、よく乾かす
- 共有のスリッパやバスマットを避ける
- 通気性の良い靴や靴下を選ぶ
- 爪白癬治療中はネイルやジェルネイルを控える
よくあるご質問(FAQ)
Q. 水虫は自然に治りますか?
A. 自然治癒はほとんど期待できません。白癬菌は皮膚の深部や爪の中に入り込むため、放置すると慢性化します。
Q. 市販薬で治りますか?
A. 軽症の足白癬であれば治る場合もありますが、自己診断では誤った治療につながる恐れがあります。
特に爪白癬は内服薬か専用の外用薬での治療が必要で、外用の場合でも1年以上の継続が必要です。
当院の特長
当院では皮膚科専門医が顕微鏡検査や抗原検査で正確に診断を行い、患者さんの症状やライフスタイルに合わせた適切な治療法を提案いたします。
また、ご家族への感染予防指導や再発防止の生活アドバイスも丁寧に行っています。
「足のかゆみ」「爪の濁り」にお悩みの方へ
「乾燥肌だと思っていたら水虫だった」というケースは少なくありません。
少しでも気になる症状がある場合は、早めにご相談ください。


執筆者
身原 京美
院長 / 身原皮ふ科・形成外科クリニック
当院は広島で皮膚科専門医と形成外科専門医が診療を行う専門クリニックです。
皮膚科の新しい治療を積極的に取り入れる一方で、高齢者医療にも長年携わってまいりました。また、院長は2人の娘を持つ母として、赤ちゃんからお年寄りまで、幅広い年代の患者さんに対応しております。女性としての視点を活かし、シミやシワなど整容面のお悩みにも親身にお応えするクリニックを目指しています。
皮膚のお悩みは、お気軽にご相談ください。
取得資格
日本皮膚科学会認定専門医 抗加齢医学会認定専門医 日本褥瘡学会認定褥瘡医師 医学博士 日本熱傷学会学術奨励賞受賞 国際熱傷学会誌BURNS outstanding reviewer受賞