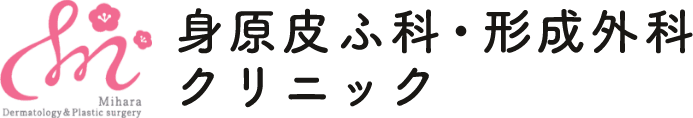アトピー性皮膚炎の注射薬について
アトピー性皮膚炎は、痒みや湿疹を伴い長く続くとても辛い病気です。
元々の体質に様々な環境因子やアレルギーが加わって発症しますが、重症になると患者さんの生活は大きく阻害されます。
10年ほど前までは重症のアトピー性皮膚炎をコントロールするのは至難の業でした。
しかしながら近年、さまざまな薬剤が開発され重症のアトピー性皮膚炎でも、皮疹がほぼない状態にまコントロールすることもできるようになりました。
そのような薬剤は生物学的製剤といわれ、アトピー性皮膚炎の病態に関わる部分をピンポイントで抑えることにより、副作用が少なくかつ効果的な治療が可能になっています。
アトピー性皮膚炎の生物学的製剤には現在4剤があり、どれも注射剤で、特定のサイトカインといわれる細胞から産生され他の細胞へと作用する物質を抑えるものです。
- デュピルマブ(商品名デュピクセント)
インターロイキン(IL)4受容体に対する抗体製剤で、IL-4とIL-13がくっつく受容体に薬剤がくっつくことでこの2つの作用を抑えます。
これにより皮膚の炎症、かゆみ、バリア機能障害を改善させます。
2週間に1回投与します。自己注射が可能と判断された方は、3回目の投与からは自己注射も可能です。
- トラロキヌマブ(商品名アドトラーザ)
IL-13抗体製剤で、IL-13 に直接薬剤がくっつくことによりIL-13 の作用を抑えます。
アトピー性皮膚炎にはILー13が皮膚のバリア機能低下や炎症、痒みに深く関わっていることが知られており、受容体抗体よりダイレクトにサイトカインの作用を抑えることが期待されます。
2週間に1回投与します。自己注射が可能と判断された方は、3回目の投与からは自己注射も可能です。
- イブグリース(レブリキズマブ)
IL-13抗体製剤で、IL-13 に直接薬剤がくっつくことによりIL-13 の作用を抑えます。
トラロキヌマブ(商品名アドトラーザ)と同様の作用機序のお薬ですが、皮膚の状態が良ければ3回目の投与から4週間間隔での投与が可能なのが大きな特徴です。
いずれも副作用として、重篤な過敏症(アナフィラキシー)のリスクが0.2%程度と頻度は低いもののあることと、結膜炎や好酸球増多症、注射部位反応などがおこりえます。
いずれのお薬も半年以上の標準治療をしているか、治療の副作用で継続できない、重症度や範囲を満たす(軽症の方は投与できません)などの投与にあたって満たすべき要件があり、すべての方に投与できるわけではありません。
当院では広島のクリニックでは第1例目にアトピー性皮膚炎の生物学的製剤を投与させていただき、その後も実績を積んでいます。
院長は生物学的製剤の医療関係者への講演も複数行っております。
アトピー性皮膚炎でお困りの方は治療経験豊富な当院にご相談ください。
参考文献:アトピー性皮膚炎における生物学的製剤の使用ガイダンス 日本皮膚科学会アトピー性皮膚炎・蕁麻疹治療安全性検討委員会
日本皮膚科学会誌 133:1817-1827,2023


執筆者
身原 京美
院長 / 身原皮ふ科・形成外科クリニック
当院は広島で皮膚科専門医と形成外科専門医が診療を行う専門クリニックです。
皮膚科の新しい治療を積極的に取り入れる一方で、高齢者医療にも長年携わってまいりました。また、院長は2人の娘を持つ母として、赤ちゃんからお年寄りまで、幅広い年代の患者さんに対応しております。女性としての視点を活かし、シミやシワなど整容面のお悩みにも親身にお応えするクリニックを目指しています。
皮膚のお悩みは、お気軽にご相談ください。
取得資格
日本皮膚科学会認定専門医 抗加齢医学会認定専門医 日本褥瘡学会認定褥瘡医師 医学博士 日本熱傷学会学術奨励賞受賞 国際熱傷学会誌BURNS outstanding reviewer受賞